| 伊勢 | 蒔田城 | 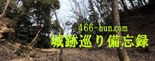 |
| 伊勢 | 蒔田城 | 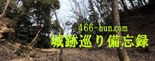 |
| ファイルNo4095 |
|
① まいたじょう |
 |
![]()
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 大矢知城 4096 |
① おおやちじょう 別名 大城 ②住所:四日市市大矢知町 ③目標地点:大矢知北町の信号 ④形式:山平城 ⑤比高:ーーm ⑥現況:公共施設 ⑦遺構等:説明板 ⑧時代/人物:戦国期/大矢知氏 ⑨満足度: 凸 ⑩最寄の駐車位置からの主郭までの所要時間:1分 ⑪撮影・訪問時期:2024年11月 県道9号線大矢知北の信号を北に折れるとすぐに道路沿いに城跡説明板があります。城跡は朝明配水場になって遺構は消滅しているようです。説明板のある道とは配水場を挟んで反対側の道(県道9号線から入る)は堀切跡のような地形をしてました。 戦国期<文明年間(1469~87年)の頃>に北勢48家のひとりの大矢知遠江守経頼が築城したとされます。大矢知氏は伊勢守護の一色氏の小守護でありましたが、文明十六年(1484年)に一色義春の死去により一色氏は伊勢守護職を失い、大矢知氏も小守護ではなくなりました。永禄十年(1567年)、織田信長方の滝川一益に攻められ降伏、信長に臣従し、柴田勝家配下となったようです。 同じ大矢知町には長倉神社あたりに大矢知砦という城跡もあり、こちらにも説明板があるようです。 |
 |
 |
![]()
近くの城・関連の城:
![]()