摴埬撪丂 |
嶳宍帺摦幵摴偺媨忛愳嶈僀儞僞傪壓傝丄怣崋傪塃愜偟導摴侾係崋慄偵擖傝傑偡丅栺侾丏俀倠倣愭丄峳愳偺僶僗掆偪傘偐偔偱塃愜偟傑偡丅栺侾倠倣愭偱崅懍摴楬偺壓傪偔偖傝丄栺係侽侽倣愭塃庤偵愢柧斅偑偁傝傑偡丅戝庤摴偼愢柧斅偺強偐傜栺侾侽侽倣庤慜偺柉壠偺娫偺摴偺墱偵偁傝傑偡丅幵偺応崌偼愢柧斅偐傜偡偖傪幬傔塃偵擖傝丄栺侾侽侽倣偔傜偄偺塃庤忋偵搶壆偲潕傔庤偺搊傝岥偑偁傝丄悢戜掆傔傜傟傑偡丅
丂
|
| 朘忛旛朰榐 |
儅僯傾偵偼傢傝偲桳柤偱偡偑丄堦斒偵偼偁傑傝抦傜傟偰偄側偄忛愓偱偡偑丄堚峔偼嬃湵偺傕偺偱偟偨丅暦偄偰偼偄偨偗偳丄偡偛偄両偺堦尵偱偡丅
崱夞偼傑偢偼潕傔庤偐傜擖傝傑偟偨丅丂偡偖偵惣抂偺擇廳嬻杧偑栚偵旘傃崬傫偱偒傑偡丅杒懁偑崅偔丄備傞偄寴杧偺傛偆偵棊偪偰偄傞傛偆偵尒偊傑偡偑丄暆傕怺偝傕偡偛偄偱偡丅丂潕傔庤摴傪恑傓偲塃嬋偑傝偺瀍宍屨岥偱偡丅搚椲偺忈暻偱偡偑丄偗偭偙偆棫攈側屨岥偱偡丅偙偺忋偑擇偺妔抂偵側傝傑偡丅擇偺妔偺搶抂傪恑傫偱戝庤曽岦偵偄偭偨傫壓傝偰傒傑偟偨丅
戝庤摴偼榌偺摴偵偁傞愢柧斅偺杒懁丄柉壠偺娫傪敳偗偨愭偺柉壠偺棤庤偵偁傝傑偡丅堦抜偺忋偵搊傞偲嵍懁偑愗娸忬丄塃庤偼幬柺増偄偵搚椲偑偁傝丄嵍忋傊岦偐偭偰墌屖忬偺摴偑懕偄偰偄傑偡丅搊傝偒傞偲摴偼嵍偵俋侽搙嬋偑傝傑偡丅嶁屨岥偵側偭偰偄傞偲姶偠傑偟偨丅偙偺忋偵瀍宍屨岥偑偁傝丄偝傜偵傕偆堦偮瀍宍屨岥偑偁傝丄愇愊傒偺嵀愓傕巆傝傑偡丅庡妔乮杮娵乯庤慜偼L帤偺妔偱庡妔偲偺娫偼怺偄嬻杧偵側偭偰傑偡丅庡妔懁偼崅偄搚椲偱偡丅丂屨岥晹偺搚椲偼暯屨岥忬偵側偭偰偄偰丄墲帪偼栘嫶偱庤慜偺妔偲宷偑偭偰偄偨偲巚傢傟傑偡丅偙偺俴帤偺妔丄昗幆偵偼攏弌偟偲彂偐傟偰傑偟偨偑丄搶懁偵偼搚椲偑偁傝丄俴帤偺旘傃弌偟晹暘偱壓偺瀍宍屨岥偵墶栴偑偐偐傝傑偡丅
庡妔乮杮娵乯偼婏楉側搚椲偑杒懁傪彍偒弰偭偰傑偡丅杒懁壓偼棫栰愳傊偺奟偵側偭偰偄傑偡丅搚椲偺堦晹偵愇愊傒偺嵀愓傕偁傝傑偡丅搚椲偺奜懁偼摨條偵惣懁丄撿懁偵傕嬻杧偑弰傝傑偡丅偙偺嬻杧偼撿懁偱偝傜偵搶偵怢傃偰丄攏弌偟偺妔丄瀍宍屨岥偺墶傑偱怢傃偰偄偰丄庡旜崻偺屨岥丄攏弌偟偺摫慄偲斀懳懁偺擇偺妔乮娵乯偺撿晹偲偺嬫夋暘偗偵傕側偭偰偄傞姶偠偱偡丅屨岥偼攏弌偟偐傜擖傞搶懁偲擇偺妔乮偵宷偑傞撿懁偺擇偐強偵側傝傑偡丅
擇偺妔乮娵乯偼潕傔庤偺屨岥傪嫬偵搚椲偑怢傃偰偄偰庡妔乮杮娵乯杧偺偲偙傠傑偱偁傝傑偡丅寢壥丄擇偺妔乮娵乯傪偙偺暘抐偡傞傛偆側搚椲偱擇偺妔乮娵乯偼搶偺嬫堟偲丄撿偐傜惣懁傊L帤宍忬偵側傞嬫堟偵側傝傑偡丅庡妔乮杮娵乯傕偦傟側傝偵峀偄偱偡偑丄擇偺妔乮娵乯偼搶擇偺妔乮娵乯偲撿偐傜惣偵L帤偵宷偑傞擇偺妔乮娵乯亙惣妔亜傪崌傢偣偨擇偺妔乮娵乯慡懱偼庡妔乮杮娵乯偺俀攞埲忋偁傞姶偠偱偡丅庡妔乮杮娵乯偲擇偺妔乮娵乯偺攝抲偼掤妔幃偭傐偄偱偡丅朘忛帪丄擇偺妔乮娵乯惣懁偵彫偝側壴傪晅偗偨怉暔偑孮惗偟偰傑偟偨丅側傫偺壴傗傠丠
偙偺忛偺嵟戝偺尒強偱偟傚偆偹丄擇偺妔乮娵乯偺奜懁傪惣懁偐傜撿懁偵偁傞嫄戝側擇廳嬻杧乮堦晹嶰廳丠乯偱偡丅怺偔偰暆傕偁傝丄嵟弶偵栚偵旘傃崬傫偱偒偨傜惡偑弌傑偡丅擇廳杧愗偺杒懁偼娫偺搚椲傕暆偑峀偔丄搚椲捀晹偵傕愺偄偱偡偑嬻杧忬偵側偭偰偄偰懠偺嫄戝側嬻杧偵偼尒楎傝偟傑偡偑丄嶰廳偺嬻杧偵尒偊傑偡丅擇廳嬻杧偑懕偔搑拞丄撿惣懁偺椦偵擖傞偲偦偙偵傕嬻杧偑偁傝傑偟偨丅彮偟嫍棧偑偁傞偺偱嶰廳嬻杧偲偼尵偄擄偄偱偡偑丄戝偒偔尒偨傜偙偙偺晹暘傕嶰廳嬻杧偱偟傚偆偐偹丅
嵟屻偵戝庤懁偺椬偺悈揷偺岦偙偆偺棫栰愳増偄偵壸梘偘応偲屇偽傟傞忋壓偵妔偑攝抲偝傟廃埻傪搚椲偑弰傞売強偑偁傝傑偡丅偙傟偼壸梘偘応偲屇徧偝傟偰偄傞傛偆偱偡丅
嫄戝側擇廳嬻杧丄偆傑偔擇廳偺杧傪摨帪偵柧椖偵尒偊傞宍偱幨恀偑嶣傟傑偣傫偱偟偨丅偦傟偩偗暆偑偁偭偰崅偔偰嫄戝偱偡丅忛愓偲偟偰偼偡偛偄堚峔偱偟偨丅擇廳嬻杧偵偼埑搢偝傟傑偡丅偄偄傕偺傪尒偨偲偄偆姶偠偱偡丅擔杤嬤偔偵棃偨偨傔丄愳嶈梫奞丄彫栰忛側偳嬤偔偺忛愓偵偼峴偗傑偣傫偱偟偨丅
|
榌偺愢柧斅
 |
|
抸忛帪婜偼掕偐偱偼側偄傛偆偱偡丅揱彸偱偼慜嬨擭偺栶乮侾侽俆侾乣侾侽俇俀擭乯偱埨晹掑擟偑擖偭偨愳嶈嶒乮拞僲撪忛乯偱愴偄偑峴傢傟偨偲偺帠偱偡丅乮撿挬尦崋乯墑尦擭娫乮侾俁俁俇乣係侽擭乯亙杒挬丗寶晲嶰擭丒巐擭丒楌墳尦擭乣嶰擭亜丄悰尨愛捗庣忢廳偼嵒嬥梂偵擖偭偰嵒嬥巵乮偄偝偛乯傪柤忔傝丄杮嵒嬥忛乮嵒嬥忛乯傪嫃忛偲偟偨傛偆偱偡丅
愴崙婜偵擖傝丄嵒嬥巵偼埳払巵偵廬偄傑偟偨丅揤惓屲擭乮侾俆俈俆擭乯丄嵒嬥巵敧戙偺忢媣偼慜愳杮忛偵堏偭偨偲偝傟傑偡丅偟偐偟丄慜愳杮忛偼嫄戝側忛偱偡偺偱丄嵒嬥巵扨撈偺忛偲偼峫偊偵偔偔丄埳払巵庡摫偱抸忛偝傟偨偐丄摉弶偼庡妔乮杮娵乯掱搙偺扨妔偺忛偱丄偦偺屻丄埳払巵偑戝夵廋偟偨忛偱偼側偄偱偟傚偆偐丠
宑挿廫嶰擭乮侾俇侽俉擭乯偵廫堦戙忢朳偑愳嶈忛乮愳嶈梫奞乯傪抸偄偰堏傝傑偟偨丅偙偺崰偵慜愳杮忛偼攑忛偵側偭偨偲巚傢傟傑偡丅
嵒嬥巵偼尦榎廫屲擭乮侾俈侽俀擭乯傑偱愳嶈忛偵嫃廧偟傑偟偨丅堦崙堦忛椷埲崀偼愳嶈梫奞偲屇偽傟傑偟偨丅嵟屻偺摉庡偺廳忢偑屻宲幰偑側偄傑傑朣偔側偭偨偨傔嵒嬥巵偼柍巏抐愨偟傑偟偨丅嫕曐幍擭乮侾俈俀俀擭乯丄埳払懞愷乮傓傜偁偒乯偑擇愮愇偱偙偺抧偵擖傝丄愳嶈埳払壠偲偟偰柧帯堐怴傑偱懕偒傑偟偨丅
丅 |

![]()




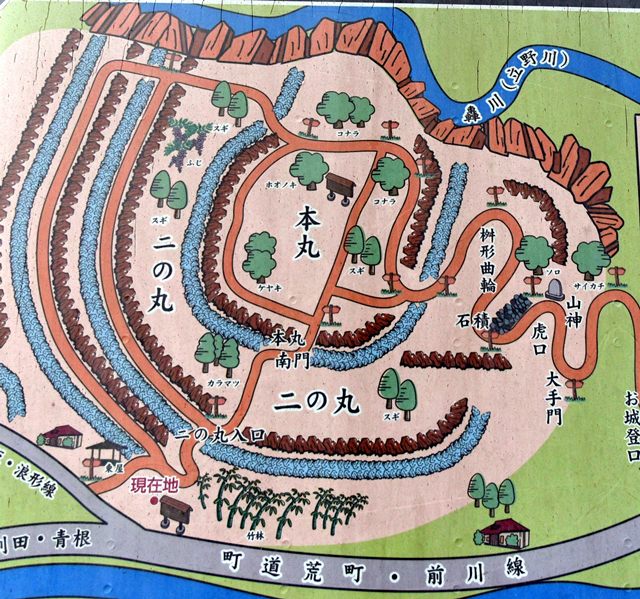









![]()
![]()