| 伊勢 | 稲垣城 | 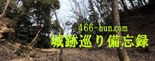 |
| 伊勢 | 稲垣城 | 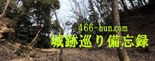 |
| ファイルNo2825 |
|
① いなかけじょう |
 |
![]()
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
![]()
近くの城・関連の城:
![]()