道案内  |
京都縦貫道の亀岡インタを下り、国道423号線を横切り、約800m先の信号で左折します。すぐに亀岡運動公園でここから約7km先、湯の花温泉西の信号で斜め左折し府道731号線に入ります。約2.5km先の本梅の信号で左折し国道477号線に入ります。約4km先が京都府と大阪府の県境で、そこから約7km先が野間稲地の信号です。さらに約1.5km先でいったん兵庫県川西市に国道は入ります。約2.5km先で再度大阪府に入り、坂を下った約100m先に信号があり、ここを右折します。約200m先を右折し、約300m先が吉川八幡神社ですが、廻りに駐車場がないので、車の場合は、右折しないでそのまま直進して能勢電鉄妙見口駅前の有料駐車場に停めた方が無難だと思います。駅から吉川八幡神社まで約1.5kmくらいです。
<国道の県境から約200m手前を左折したところにある廃業となった旧妙見の森ケーブルの黒川駅周辺は駐車スペースがあるので距離的には吉川八幡神社には近いかもしれませんが、何時までここのスペースで停められるかは不明ですし、自己責任で駐車してください。>
|
| 訪城備忘録 |
吉川八幡神社から登りますが、本殿を正面に右手方向に登り口があります。登り口には地面に落ちてしまっていますが「吉川城(1.5km)」という標識があります。比高で130mですので、1.5kmは無いと思います。20分くらいで城跡に到達します。途中途中に城跡案内標識があります。
城域は基本単郭です。主郭は丸い感じです。神社から登ってくると東側端に達します。主郭下周囲を帯郭と横堀との混在した空間が取り囲んでいますが、東側は堀切状でやや他より深いです。斜面には人頭程度の石が散乱していて石垣が崩れたようにも見えます。主郭には東側、北側の一部、西側の一部が土塁状になってます。主郭内はやや盛り上がった感じで、削平度は甘い感じです。西側下は空堀上になって南西側まで続いていて、南側は帯郭状です。北側は一部は空堀状ですが、帯郭状の削平地でした。主郭北側、やや東寄りに虎口と思われる開放部があります。石列があると資料にはありましたが、よくわからなかったです。西側の空堀の下に細長い帯郭状の削平地があり、標識には「西郭」と書かれてありました。 その下はおおきな鞍部でその向こうに登ると尾根が続いています。
この城は吉川井戸城が本城で、詰の城と言われるようです。
麓の吉川八幡神社には阪急電車の頭だけが三両分置いてあります。宮司さんが鉄ちゃんらしいです。(笑) 時期もあるんでしょうけど、妙見口駅から妙見山へ登られる方が多かったです。 同じような服装、靴でも城跡へ向かうのは私だけでした・・・(笑)
|
城址碑
 |
1492年(延徳四年)、吉川長仲が築城したとされます。天正元年(1573年)、一族とされる塩川長満に攻められ吉川城の吉川貞満(定満)は滅亡したとされます。 この吉川城は山城の吉川城(長棚城)ではなく、吉川井戸城ではないかとされます。吉川氏嫡流が滅亡後、塩川長満の一族の吉川頼長が城主となり、次いで、天正四年(1586年)長満の子の吉川頼国が城主となりましたが、天正十四年(1586年)に豊臣秀吉によって塩川氏は改易され、吉川氏も同様であったようで、この頃に吉川井戸城、吉川城は廃城になったと考えられます。
|
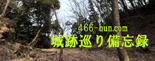
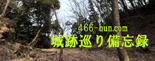

![]()









































![]()
![]()