| 日向 | 飫肥城 | 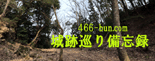 |
| 日向 | 飫肥城 | 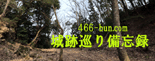 |
| ファイルNo4252 |
江戸期伊東氏の居城
|
① おびじょう |
 |
![]()
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
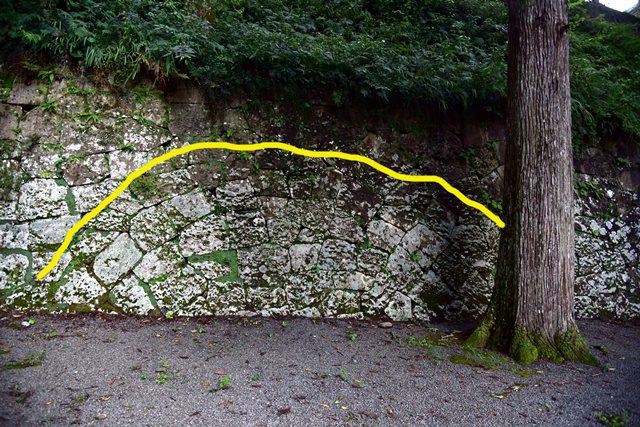 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
![]()
近くの城・関連の城:
![]()