道案内  |
山陽自動車道の龍野西インタを下り、料金所を出て約200m先のインター前の信号を左折し県道121号線に入ります。約1.4km先の信号で右折し国道2号線に入ります。約13km先が有年橋で千種川を渡ります。渡ってすぐを右折し川沿いを進みます。約700m先で斜め左に登る道があり、ここに入ります。約600m先に【登城道④】の登り口があります。反対側に後藤陣山城の登城口があります。
あるいは、国道2号線の有年橋から約300m右手が有年公民館でこの奥から登るルートがあります。【登城道①】 さらに、国道2号線の有年橋から約1.2km先の東有年の信号を右折します。約200m先右手が有年八幡神社で【登城道②】の登り口で、そこから約100m先右手に薬師堂からの【登城道③】の登り口があります。②、③には集落外に駐車するしかないです。①は公民館が広いですが、登城道は長そうです。④は路駐するしかないですが、トラックがよく通りますので、車を寄せるところに注意です。
|
| 訪城備忘録 |
通常は①か③から登るのでしょうけど、ナビに任せて走ったら④の登城口に連れていかれました。(笑) ④の登城道は北側斜面の沢を細い道をジグザクで登ります。倒木とか大石で登りにくく、急ではありますが、距離は短いですね。
登って行くと北斜面に畝状竪堀が見えてきます。畝状竪堀を左手に廻り込むと北段郭群の一番下の郭<北5郭>に至ります。この郭はけっこう大きいです。その上、北4郭を経由し北3郭の先端には残存石垣があります。その横には畝状竪堀が上から見ることができます。北2郭を経由し西郭の下の北1郭まで行きます。西郭との切岸はなかなか高いです。
西郭は尾根東西に表に長く幅があります。中央に大型土杭と表記された大穴があります。穴蔵と言われるようです。これより小さい土杭が四つほどありました。大型土杭のそばには水堀と表記された長い窪みがあります。これも乾燥しているのでよくわかりませんでした。
西郭の西端、北西端側と南西端側に段郭群があります。北西端側は西郭との高低差もなく、わりと大きめの段郭が三段ほどあります。南西端段郭群は見てません。
西郭の東端から斜面で主郭まで続きます。その間に最初は低い切岸で三つの段郭、その後主郭まで急に斜面がきつくなりふたつの段郭を経て主郭になります。眺望はいいです。周囲の城跡、後藤陣山城、鍋子城、鴇ケ堂城などが望めます。主郭より北東側に下りていきます。東郭群は、主郭下は削平度が甘い郭ですが、北東先端郭<東3郭>は西郭ほどではないにしても大きく広い郭で、先端側に石組井戸と石積みが残ります。東郭群を下りると東郭下には明瞭な土橋があり、土橋の左手にはV字状の堀切が残ります。土橋を守るように両サイドに大きな竪堀があり、土橋の南側にはそう長くない横堀があります。このまま尾根を下っていくと放亀山古墳を経て有年公民館に至ります。
主郭に戻って南側に下りると南段郭群です。あまり技巧的とは言えないです。先端に見張り台という標識でした。このまま下りると有年八幡神社に至ります。西郭の中間まで戻り、南斜面には南西段郭群があります。こちらの段郭は横に長い郭が連なります。削平度もしっかりしてます。つぶて石の集積場所がありました。この段郭群の東側、南段郭群までの間の斜面に畝状竪堀があるように書いてある資料もあります。横移動できる小道もあるので見ることができますが、明瞭な竪堀とは言い難く、どうなんだろうかという感じでした。
山頂部に西郭、主要郭、東郭群が配され、そこからの尾根、斜面に多くの段郭群がありました。山頂部全体を城郭として使用し、城郭範囲以外には明瞭な尾根はないので大きな堀切というようなものはありませんが、竪堀は幅のある明瞭なものが多いです。(南斜面は除き) 主要部の郭は大きく、各段郭もそれなりに大きな広さがあり、相当に強力な城郭かと感じます。
|
主郭城址碑
 |
南北朝期の暦応年間(1338~42年)に本郷掃部助直頼(赤松則村<円心>の孫、赤松範資の子>が居城したという史料があるようで、この頃に築城されたようです。その後、長禄年間(1457~60年)の頃には赤松氏の家臣の富田(戸田)右京が在城しましたが、天文年間(1532~55年)に浦上宗景によって滅ぼされたようです。さらに、元亀年間(1570~73年)には赤松氏の家臣の小田(太田)弾正が在城しますが、天正三年(1575年)には宇喜多氏の城となっていたようです。天正六年(1578年)頃には羽柴秀吉が播磨を支配し、天正七年(1579年)には宇喜多氏が織田氏に降り、天正九年(1581年)に秀吉が播磨の破城令を出した経緯の中で有年山城もこの頃に廃城になったようです。
|
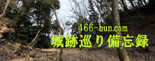
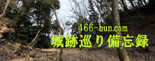

![]()





















































![]()
![]()