| 攄杹 | 弢娾忛 | 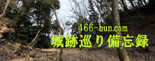 |
| 攄杹 | 弢娾忛 | 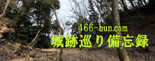 |
| 抬操俶倧係侾俀俆 |
|
嘆丂偨偰偄傢偠傚偆丂 |
 |
![]()
| 丂丂 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 丂丂 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
![]()
嬤偔偺忛丒娭楢偺忛丗
![]()