道案内  |
東北中央自動車道の米沢中央インタを下り、県道1号線を米沢市街地方面に向かいます。約3km先、春日橋を越えた信号で国道121号線に合流します。約3.5km先の信号で国道は右折です。約400m先を左折し、小さな橋を渡った先で右手に発電所があり、そのまま進むと右手が大きな広場になります。館山東館という居館跡にあるようです。ここの奥から登ります。
|
| 訪城備忘録 |
訪城時、最大の見所の石積み枡形虎口にブルーシートがかかっていて残念な姿でした。私の訪城は4月中旬、5月の連休にはブルーシートも取り外されたようでした。
館山東館は広い広場になってます。「私有地ですが大歓迎」という木柱が立ってました、(笑) 広場を奥に行くと登城口です。大きく二度折れと道を登ると二の郭の虎口です。見た目はすり鉢状の空間です。尾根に登ると二の郭で東西に長く幅もある郭です。
二の郭の西側ヘ進むと主郭とを隔てる土塁が横たわります。その土塁の北端にここの見所である石積みの枡形虎口があります。訪城時は発掘調査の後でしょうかブルーシートがかけられ石塁の全体は見られませんでした。枡形を作る土塁の施された石積みは小さな石が張り付いているようにみえます。栗石があって石垣の石がなくなっているという事なんでしょうか。破城の処置と言う事のようです。基部には石列がまだ残っているところもありました。
枡形虎口を抜けると主郭ですが、二の郭と主郭の間に土塁と枡形虎口の主郭側に主郭とを隔てるように堀が横たわっています。この堀は北側斜面へ堅堀として落ちています。虎口から主郭へはこの堀を木橋で渡って入るのでしょうけど、郭側に堀があるというのが珍しい感じがします。堀を掘るなら主郭側にも土塁があるのが普通と思ってしまいます。当然、主郭側には柵か土塀があるんでしょうけど、改修途中で終わってるんかな? 主郭は西側に高い大土塁が横たわります。その北端に西側の虎口があります。北側の土塁が鍵状に曲がり、大土塁の端とで枡形というより食い違い虎口的で、虎口から少し離れて横たわる土塁が遮蔽土塁の役目をしてました。
北端の通路を抜けると主郭西側(大土塁の西側)堀切のところです。堀底の地下には発電所の水路があります。それを抜けると三の郭になります。南北に長い長方形ですが、他の二つの郭からすれば小さい郭です。この三の郭の南端は頂きとなっていて物見台という事です。この物見台の西側に城域西端の堀切があります。深くて、斜面も鋭い堀切です。
枡形虎口は残念でしたが、全体的に整備された見やすい城跡でした。
|
進入路の説明板
 |
築城時期は定かではないようです。伝承では鎌倉期に奥州藤原氏の家臣、新田経衡の居館が始まりと言われますが定かではないようです。
天文十七年(1548年)、伊達晴宗が桑折西山城から米沢城に本拠を移したとされ、その米沢城は、現在の米沢城の位置と同じか、館山城の事かは定かではないようです。
天正十二年(1584年)、伊達輝宗が子の政宗に家督を譲った際に館山城を隠居城と定めたとされます。翌年、輝宗が死去し、天正十五年(1587年)以降、政宗が大改修に着手したようですが、天正十九年(1591年)、豊臣秀吉の命で政宗は岩出山城に移封したため、館山城は廃城になったとされます。
伊達氏の後、この地は蒲生氏、上杉氏が領有しますが、上杉氏が館山城を改修した痕跡があるようです。
|
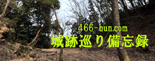
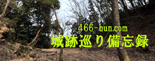

![]()












































![]()
![]()