道案内  |
東北中央自動車道の山形中央インタで下り、県道18号線で山形市街地へ進みます。約1.2km先、西田の信号で直進して県道49号線に入ります。約1.6km先の信号で直進して国道112号線に入ります。約300m先の信号を右折し約200m先が北不明門です。ここを入り、すぐを左手に行くと城内の駐車場です。北不明門のそばに城址碑があるとの事ですが見落としました。^^;
|
| 訪城備忘録 |
今回の東北城巡りは桜の時期でしたが、できるだけ桜の満開は避けて日程を廻したつもりでしたが、山形城は満開過ぎで快晴も相まってすばらしい桜でした。ただ、二の丸東大手門の橋から桜とお堀と新幹線を撮る方が数名動きませんし、全体に人も多いので、撮りたいショットとはいかなかったかな。
本丸を二の丸が取り囲み、その外側を三の丸が取り囲むという輪郭式縄張です。三の丸は市街地化してしまってますが、二の丸の周囲を土塁が巡り、その外側を水堀が巡ります。二の丸は一辺約500mの規模です。東大手門が復元され、北不明門、西不明門、南大手門の石垣、枡形が残ります。二の丸東大手門の枡形の規模は江戸城並みと言われています。二の丸東大手門から郭内に入ると最上義光の像があります。「義光」、どうしても「よしみつ」と呼んでしまいがちですが、「よしあき」です。 土塁についても北側の西側で張り出していたり、南大手門近くでも屈曲を入れて横矢を意識したものになってます。その土塁には肴町向櫓の石垣が整備されてますし、屏風状に建てられた土塀の跡の礎石があったりします。南東端の巽櫓石垣も復元されています。
西不明門は二の丸の南西隅にありますが、枡形の石垣がいいです。ましてや桜の花びらが覆いかぶさってました。二の丸の東側沿いは仙山線が通ってます。これは山形新幹線も供用しているため、たまに新幹線が城の横を通って行きます。「城と桜と新幹線」、確かに絵になるかも。(笑)
本丸については、城内が運動公園になっていた時代があり、現在も発掘調査、整備中ですが、大手橋、一文字門やそれに続く枡形、石垣、堀が復元されています。石垣については発掘調査で七段ほど出土したものを積み直し、上部を加えたという形のようです。発掘調査、整備は進行中です。
なお、移築建物として、万松寺山門(山形市平清水)は旧大手門<義光が改修前の門>が、宝光院本堂(山形市八日町)は御殿(伝承)が移築されているようです。
さらに三の丸の土塁、石垣の痕跡などが市内に残ります。
縄張は単調と言うか近世の最先端の縄張ですね。最上氏時代の力を思わせる遺構でした。良い天気で、桜と城はやっぱり良いですねぇ。
|
延文元年(正平十一年・1356年)、羽州探題として入った斯波兼頼が翌年この地に初期山形城を築城したようです。山形斯波氏はその後に最上氏を名乗りました。元亀元年(1570年)頃に最上義光(よしあき)が家督を継いで最上氏第十一代当主に就いたようです。天正十八年(1590)の小田原の役に参陣し、豊臣秀吉より二十四万万石を安堵されました。慶長五年(1600年)の関ケ原の戦いを乗り切り、江戸初期には五十七万石となり、山形藩初代として山形城を大改修したようです。元和八年(1622年)三代藩主家信(義俊)の代に、最上騒動で改易され(近江蒲生郡大森<現:東近江市>に一万石(のちに五千石の交代寄合)、その後を鳥居忠政が二十四万石で入封(寛永十三年(1636年)にいったん無嗣断絶)、鳥居氏の後は保科氏、奥平松平氏、奥平氏などなどが短期間に入れ替わりで入封転封が繰り返されました。その間、徐々に石高が小さくなっていき、江戸後期の秋元氏の時代は六万石、幕末の水野氏は五万石の小藩で、巨大な山形城を維持できずに相当に荒廃したようです。
|
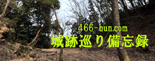
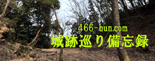

![]()






























































![]()
![]()