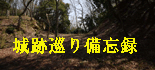道案内   ←駐車場 ←駐車場 |
東北自動車道の一関インタを下り、国道342号線を一関中心部へ進みます。約1.5km先の大槻の信号で右折し国道4号線(国道342号線と供用)に入ります。約800m先の十二神の信号で国道342号線に入ります。約1.5km先、磐井川を渡った先の上の橋の信号で右折し釣山通りに入ります。約200m先の左手が公園駐車場で、右手が釣山公園登り口です。
|
| 訪城備忘録 |
釣山公園一帯が一関城ですが、明瞭は山城遺構は無い感じです。雨の中の訪城でしたが、公園ですので千畳敷までは登れました。千畳敷が主郭で、田村神社の背後の高まりは見張り台か櫓台の名残のようです。また、三春の滝桜の枝分けの愛姫桜があります。中腹に藩主の井戸と言う月見の時のお茶会用の井戸が再現されています。
陣屋跡は裁判所敷地等になっているため遺構はありません。近くに沼田家武家屋敷と言う建物が残っています。沼田家は江戸期の家老の家だそうです。
なお、一関陣屋の移築門として平泉の毛越寺の山門として長屋門が移築されているようです。
|
説明板
 |
|
築城時期などは定かではないようです。伝承では、大同年間(806~810年)、坂上田村麻呂が陣地とした、天喜年間(1053~58年)、磐井五郎家任(安部貞任の弟)が砦を築いた、康平年間(1058~65年)、源頼義、頼家が陣地としたなどのものがあるようです。<前九年の役(1051~1062年);東北の豪族安部氏と国司源頼義の覇権争いで、頼義に清原氏に加担し安部氏を滅ぼしたもの>
戦国期に入り、天正年間(1573~92年)に葛西氏の家臣の小野寺道照が釣山に居城を築いたとされます。天正十八年(1590年)、豊臣秀吉の奥州仕置で葛西氏は改易となり、翌年葛西氏は一揆を起こしますが、秀吉の再仕置で鎮圧され、その後は伊達政宗の所領となりました。一時、政宗の子の宗勝が三万石で藩主となりましたが、伊達騒動で宗勝は配流されいったん一関藩は消滅します。その後、天和二年(1682年)、伊達家は、奥州仕置で改易となった政宗の正室愛姫の実家の田村氏を岩沼にて仙台藩二代の忠宗の子の宗良に田村氏を継がせ再興し岩沼藩とし、ついで、岩沼より三万石で宗良の子の田村建顕(宗永から改名)が一関に入部し、以後、明治維新まで続きました。ただ、山城は使わず、麓に一関陣屋を築いてます。
|

![]()











![]()
![]()