道案内   ←駐車場 ←駐車場 |
東北自動車道の花巻南インタを下り、県道299号線を南下します。約700m先の信号を左折し県道12号線に入ります。約2km先の信号で左折し県道103号線に入ります。道なりに約2.2km先の信号で逆Vに右折し県道297号線に入ります。約300m先の坂本町の信号で直進します。約400m先、本丸橋を渡った先で左折したところが駐車場です。城跡は右側の丘の上です。
|
| 訪城備忘録 |
本丸橋の手前の信号で右折し坂を登ると本丸横で、反対側は花巻小になるんですが、この道は一般車は通行を制限されているらしく、また、当然ですが駐車場もありません。下の駐車場から徒歩で登るのがいいです。
城郭遺構として残るのは本丸部分のみです。二の丸・三の丸は公共施設や宅地が建っており、堀などは残;っていません。武徳殿が建っている付近に東御門跡があり、この周辺に土塁は少し残ります。
本丸は南北に長く丘陵の北端にあります。東端に菱櫓(跡)があり、二の丸と土橋で繋がる御台所前御門周辺に土塁が残ります。その周辺が本丸公園になってます。本丸南側には鐘搗堂前堀がL字に残ります。土橋の反対側には御囲穀御蔵前堀がありますが、藪でよくわかりません。本丸の西側、鐘搗堂前堀側にも土塁が残り、本丸井戸も残ります。さらに西御門が復元されてます。西御門は土橋で繋がり、この土橋の下は石垣が残ります。土橋の先は南北に細長い郭で往時は鐘搗堂前堀を含めた堀で囲まれた郭のようで馬出し機能があったようです。
三の丸南東側の鳥谷崎神社には円城寺門が移築されています。この門は花巻城では搦め手門でありますたが、元々は二子城(飛勢城)の門であったものを移築されたものとの事です。円城寺門の前の道を西に進むと武家屋敷が二軒残り、その先は花巻市役所ですが、ここに大手門跡と時鐘堂があります。時鐘堂の鐘は元々は盛岡城のもので、「南部盛岡城楼鐘銘」という銘文が刻まれているそうです。盛岡城では鐘の音が小さく、大型の鐘に取り替えられ、元の鐘は二代藩主重直の許可をもって花巻城に移されたようです。
|
城址碑
 |
|
伝承では安部頼時が築城した十二柵の内、鶴脛柵がここであったとも言われるようです。前九年の役(永承六年(1051年)から康平五年(1062年))の終息後に東北地方を統治した鎮守府将軍の清原武則、武貞親子が居城としたと言われます。文治五年(1189年)、奥州藤原氏が滅亡し、この地は稗貫氏(ひえぬき)が支配し長く十八ケ城を本城としていましたが、享禄年間(1528~32年)、この地を鳥谷ケ崎城として本拠を移しました。
天正十八年(1590年)、豊臣秀吉の奥州仕置により稗貫氏は改易となりました。ここには秀吉の代官として浅野長政が入り、後に浅野重吉が城代として駐留しました。この年、稗貫氏の一揆により一時は島谷ケ崎城も稗貫氏の手に落ちますが、天正十九年(1591年)の秀吉の奥州再仕置により一揆は鎮圧されこの地は南部領とされました。
南部信直はこの地に重臣の北秀愛(ひでちか)を入れ、城を改修し花巻城と改称しました。秀愛死去後、父の信愛(松斎)が城代になります。慶長十八年(1613年)に信愛が死去し、藩主南部利直は、子の南部政直に二万石で城代とし花巻城の改修を完成させました。一国一城令以降も南部氏の存続城となり、政直が寛永元年(1624年)に急死後は、城代が置かれました。
|
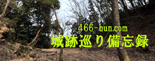
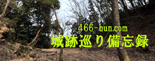

![]()




























![]()