道案内  |
東北自動車道の浪岡インタを下り、料金所の先の信号で左折し県道285号線に入ります。約5km先の浪岡の信号で左折します。約500m先の信号で左折します。<約800m先右手から浪岡城は見えてます。> 約1.5km先の信号を右折します。約300m先を右折した先が浪岡城跡案内所で駐車場もあります。 徒歩の場合は案内所まで廻らず、北館から入れますし、浪岡川沿いの内館下からも入れます。
|
| 訪城備忘録 |
主要七つの島のように独立した郭があり、群郭式の縄張です。その中で、内館(うちだて)が主郭相当で、一番大きな北館(きただて)が家臣団の屋敷群であったようです。
郭郭の間は堀になっていて、堀の真ん中に土塁が通っていて堀自身は二重堀のように見えます。内館と猿楽館の南下の堀は相当に長く、西館と北館の間の堀と土塁は内館から北に伸びる様が良く見えるので、印象的で、内館・猿楽館の南下堀とT字形で交わるので、面白い景色です。さらに、東館と北館の間の堀と土塁は特に土塁の幅があり、現地では中土塁と説明されています。 あまり、関東以西では見ない城跡の縄張ですので興味深いですが、浪岡川の河川段丘上のほぼ平城ですので、防御性は低そうに感じます。
|
浪岡八幡宮の道の反対側にある城址碑
 |
築城時期、築城者は諸説あるため定かではないようです。発掘調査では12世紀の遺物もあるようで、奥州藤原氏に関連した豪族の館があった可能性もあるようです。室町期に入り、北畠顕家の子孫と言われる浪岡北畠氏は浪岡に入りますが、浪岡城をすぐに居城としたわけではないようです。浪岡城を居城としたのは、明応四年(1495年)頃、北畠顕義と言われるようです。浪岡北畠氏は浪岡御所と呼ばれるようです。その後、永禄五年(1562年)、川原御所の乱と言う北畠氏内紛があり衰退していきます。天正六年(1578年)、北畠顕村の時に大浦(津軽)為信に攻められ落城し、顕村は自害し、浪岡城は廃城になった様です。
|
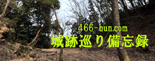
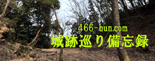

![]()




































![]()
![]()