道案内  |
秋田自動車道の八竜インタから国道7号線能代パイパスに入ります。約15km先、能代東インタを下ります。「かいらげふち」の信号で右折し国道7号線本道に入ります。約2km先の桧山入口の信号で右折し県道4号線に入ります。約3km先、県道294号線との分岐ですがそのまま県道4号線を進みます。分岐から約1.2km先を左折し約400m行ったところが集落内の道との合流でそこに城跡に登る林道入口があります。そちらに入って、約1.4km先が駐車場です。
|
| 訪城備忘録 |
雨の日の訪城でした。ただ、ここは主郭下まで車で行けるため、少し無理はできると思い訪城しました。ただ、斜面を下りたり、主要部以外に行くのは諦めました。
車で三の郭まで登ります。途中、車道の左上に大きな二重堀切を見ることができます。三の郭は長方形のような郭で、先端が高い土塁となっていて櫓台のようです。この下に先ほどの二重堀切があります。二の郭に上がります。今回は行かなかったですが、西に伸びる尾根があり、その先にも堀切があるようです。二の丸の上が主郭です。広いという印象です。こちらも今回は行かなかったんですが、主郭の南西下に郭があり、これからもうひとつ西に尾根が伸びていてここにも堀切があるようです。主郭の東下の郭から主郭を見ると切岸が高いです。
主郭より東尾根の郭に行きます。幅のある尾根です。二つ目の郭の東側では南北に土塁が伸び、北東端には土塁作りの枡形虎口があります。さらに虎口を出ると大きな堀切で土橋が架かっています。この堀切から将軍山と呼ばれる頂部まで郭や迷路になったような土塁が続きますが、どうも意図で構築されているのかつかめませんでした。 将軍山の頂部は檜山城の詰めの城部分という事のようです。将軍山の南東下には郭を一つ挟んだ先に尾根を切断する大堀切がありました。 さらに将軍山の北側尾根の平坦地は屋敷跡と呼ばれた広い郭です。この北端には高い土塁に囲まれた館神堂がありました。
館神堂の先は行ってません。堀切を越えた先で西に尾根が90度曲がり中館の郭群が続くようです。
麓の集落の道沿いにある浄明寺山門は檜山城の移築とされます。
全体として大きな山城であり、堀切は多数残り、かつ、大きくて深いです。尾根上の郭も連続して繋がり、ブロックに分けられる感じでした。 戦国から江戸初期の縄張が見られるという事のようです。
|
駐車場への登り口と説明板
 |
安東氏は元々は藤崎城(南津軽郡藤崎町・永保二年(1082年)築城)を発祥とし、その後、津軽の十三湊(とさみなと)を本拠としてました。一族は大きく二家に分かれ、津軽にとどまった安東氏を下国家(しものくにけ)、南下した一族を上国家と呼ぶようです。上国家(かみのくにけ)はのちに湊安東氏となります。津軽に残った安東氏(下国家)は南部氏に破れ、一時北海道(蝦夷)の道南に逃れて、勢力の立て直しを行い、康生二年(1456年)頃、安東政季(まさすえ)が檜山に進出し、葛西秀清を追い檜山を本拠として支配しました。
政季の子の忠季が明応四年(1495年)に檜山城を築いたとされます。(なお、このころまでは安藤と表記であったようです。) 忠季の後、尋季(ひろすえ)、舜季(きよすえ)と続き、舜季の子の愛季(ちかすえ)は元亀元年(1570年)に檜山安東氏、湊安東氏を統一しました。
天正五年(1577年)、家督を業季(なりすえ 天正十年(1582年)に病死)に譲り、愛季は脇本城に移りました。天正十五年(1587年)、愛季が死去し、家督は次男の実季(さねすえ)が継ぎました。天正十九年(1591年)、実季は安東姓から秋田姓に改称しました。その後、慶長七年(1602年)秋田実季は常陸穴戸に移封となってます。
檜山城は佐竹氏の領有となり、小島義成が城代として入り、後、多賀谷宣家(佐竹義重の子、多賀谷重経の養子)が入り、城を改修したようです。元和六年(1620年)の一国一城令で檜山城は廃城になりました。多賀谷氏は麓に居館を築いて江戸期この地を支配したようです。
|
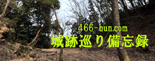
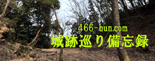

![]()























































![]()
![]()