道案内   ←登り口 ←登り口 |
舞鶴若狭自動車道の綾部ジャンクションから綾部宮津道路に入り、さらに宮津天橋立インタから宮津与謝道路に入り与謝天橋立インターで下り、国道176号線へ左折します。約2.5km先の石川の信号で斜め左折の国道176号線に入ります。約1.2kmの亀山の信号で右折し府道76号線に入ります。約2.5km先の幾地の信号で右折します。(府道76号線のままです。) 約500m先の信号で右折し集落内に入ります。約300m先、養源院の西側の路地に左折します。約50m先の正面に赤い鳥居と「伊久知城址」と刻まれた城址碑があります。この背後から支尾根を登ります。
|
| 訪城備忘録 |
夏場の山城でしたので、午後五時過ぎから登りました。鳥居を越え、獣除けの柵のゲートを越えたら主郭までの支尾根の登城道を登ります。元々は稲荷神社の参道になっていたようです。
支尾根を登って行くと南東の段郭群が主郭まで続きます。けっこう大きな段郭です。中腹で斜面をU字に掘り込んである箇所があり、その右手も大きな段郭です。この坂虎口状は神社の参道の跡なんでしょうね。虎口だと面白いのですが・・・。 ここからさらに主郭に向かって坂道が続きます。中心部は東に広い平坦地があり、「幾浦冨来稲荷神社跡」の石碑が立っています。他のサイトを見ると15年前には社殿が建っていたようですが、今はありません。西に一段上がった所が主郭です。主郭の西は副郭、(仮称)三の郭とあり、その先はいったん大きく高低差があります。
高低差は10mはあるんでしょうか?、下りると典型的な堀切形状になります。しかし、堀切形状の横に尾根を削り込んで北側を削り残しの土塁をL字状に残した広い郭があります。また、南側には本来は堅堀でしょうけど、南の段郭群への虎口になってます。 ここは改修の跡なんでしょうかね? 削り残しの土塁はさのまま西側の郭に繋がってます。この先、また大きな高低差があり、下に広い郭がありますが、日没も近づいたため無理はせずここで引き返しました。
戻って先ほどの堀切の南側の堅堀状の通路を下ります。下りて振り向くとまさしく堅堀から見た堀切ですね。5mも下りたら左手の方に行くと南の支尾根にやはり大きな段郭が三段ほどありました。ここもまだ先があるかもしれませんが、引き返しました。南段郭の斜め東上に登って行くと主要部の下に出ました。
小さな城域の城のつもりで登ったんですが、案外に広い城域の城でした。主郭・稲荷神社跡の東側下、高低差10m以上の下に谷なのか堀切なのかと言うものがあるようです。郭群と次の郭群の間の高低差が非常にある城でした。日中35℃越えでとても山城には登る元気がないため、夕方に登ったので、大きな高低差を下りる時間がなかったです。
|
城址碑
 |
築城時期、築城者は定かではないようです。戦国期は石川氏の主要城郭であるようです。城主には石川左衛門尉秀門の名があるようです。天正十年(1582年)、細川藤孝は宮津城で一色義定を謀殺しました。秀門もこの時死去したようです。義定の叔父の義清は弓木城に籠城しましたが、細川氏の攻撃を受け討死し一色氏が滅亡しました。この時、秀門の子の秀俊も討死しました。幾地城も細川藤孝(幽斎)、忠興親子に攻められ落城したとされます。秀門の次男の五右衛門(五良右衛門)は盗賊となり、世にいう石川五右衛門であったと言われているようです。
|
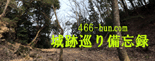
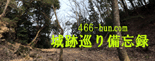

![]()




























![]()
![]()