| 丹後 | 石川城 | 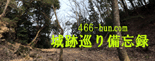 |
| 丹後 | 石川城 | 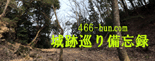 |
| ファイルNo4201 |
|
① いしかわじょう |
 |
![]()
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 東の尾根郭群 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
![]()
近くの城・関連の城:
![]()