| 丹波 | 福知山城 | 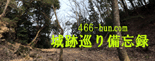 |
| 丹波 | 福知山城 | 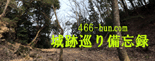 |
| ファイルNo1600 |
|
① ふくちやまじょう |
 |
![]()
| 道案内 |
|||
舞鶴若狭自動車道の福知山インタで下り、国道9号線を市内に向かいます。約3.5Km先で土師川を渡り、高架を下りた先の東堀の信号を右折し、府道55号線に入ります。約700m先でJR山陰本線のガードを越え、約350m先の信号で左折し約150m先の左手に公園有料駐車場があります。 |
|||
| 訪城備忘録 | |||
2006年、約十五年ぶりに福知山城を訪れました。前回は1991年だったか1992年だったかですが、京都市内から国道9号線をひたすら走って行った記憶があります。(笑) その後、何度か訪城しています。 天守は復興天守ですが、外観は下見板張り風に建てられていて趣があります。本丸周囲は石垣ですが、天守台石垣と付け櫓下以外は積み直し(再構築)でしょうかね。天守台石垣(増設部分と付け櫓下は江戸期かな)は明智光秀当時のもので、転用石を多く使用されており面白いです。この転用石、築城を急いだためではありますが、きちんと供養され積まれたと伝わります。確認されているだけで500以上の転用石があるそうです。天守台に継いだ跡があり、江戸期に増設された部分のようです。本丸には大きな井戸と番所が現存しています。本丸西側には二の丸が台地続きであったようですが、今は削られて谷状になって公共施設が建ってます。その西側に伯耆丸の台地があります。 二の丸と伯耆丸の間は堀切になってたようです。 由良川越しの天守、伯耆丸からの天守(夜景)もなかなかよかったですね。 2025年に再訪城しました。久しぶりに天守に入館したのと市内の移築門等を廻ってみました。門が七ケ所、能舞台が1ケ所でした。 【移築門等】 ① 明覚寺山門 高麗門 扉上部が格子になっている。 福知山市呉服町 ② 大手門跡説明板 福知山市内記2丁目 ③ 法鷲寺(ほうじゅじ)山門 高麗門 隅立て四つ目紋(朽木家)の付いた鬼瓦。 福知山市下紺屋 ④ 正眼寺山門 高麗門 門の金具が銅製のため銅門(あかがねもん)と呼ばれ、福知山城本丸に 移築されている番所とともに二の丸の虎口にあったもの。 福知山市寺町 ⑤ 照仙寺山門 長屋門 ここだけ説明板が無い。 福知山市堀 ⑥ 一宮神社 能舞台 福知山市野家 ⑦ 観瀧寺山門 薬師門 福知山市榎原 ⑧ 観瀧寺南門 高麗門 福知山市榎原 ⑨ 瑞林寺山門 薬師門 福知山市夜久野町板生 |
|||
小笠原長清の末裔とされる塩見頼勝が横山城を築いたのに始まります。 天正三年(1575年)に始まった明智光秀の丹波平定は、天正七年(1579年)に横山城の塩見信房、八上城の波多野氏を降し丹波一国を平定、光秀は横山城を改修し福智山城と改名しました。築城には付近の寺社などから墓石や五輪塔等を多数供出させたもので、今も天守台に残ります。福智山城には甥で女婿の明智秀満が居城しました。天正十年(1582年)の本能寺の変で光秀が織田信長を倒しますが、山崎の合戦で羽柴(豊臣)秀吉に破れ、福智山城は天正十四年(1586年)に羽柴秀勝の家臣の杉原家次が在城、その後、青山氏、桑山氏、小野木氏が城主となりました。 慶長五年(1600年)の関ヶ原の戦いでは、小野木重勝は西軍に属したため、自刃しました。この年、有馬豊氏が入封し城を大改修し整備しました。以後、岡部氏、稲葉氏、深溝氏と城主が変わり、寛文九年(1661年)に朽木稙昌が32000石で入封し、朽木氏が福智山から福知山に改めました。以降、朽木氏が14代続き、明治維新まで続きました。 |
|||
 |
 |
 |
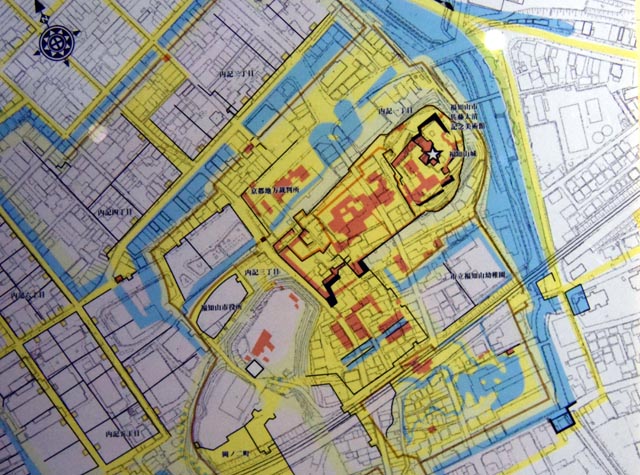 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 移築門など |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
![]()
近くの城・関連の城:
![]()